![]()
さし木するために切り取った植物体の一部を「さし穂」といいさし木の方法はさし穂を取る部位によって種類が分けられる。
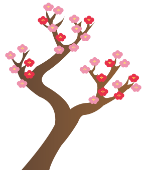
※ 葉ざし
葉を切り取ってさす方法で一枚の葉をさす全葉ざしや、葉柄をつけてさす葉柄ざし一枚の葉をいくつかの葉片に切り取ってさす片葉ざしなどがあります。
※ 葉芽ざし
一枚の葉とそのつけ根の芽、それにともなうわずかな茎をつけてさし穂にします。
※ 枝ざし・茎ざし
枝や茎をさし穂に用います草花の場合は「さし芽」ともいう一本の枝でも先端部を用いるものを天ざし、頂芽ざしそれより下の中間部を用いるものを管ざしといいます。
※ 根ざし
根や根茎の一部を切り取りさし穂に用いるもので根伏せともいう。
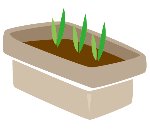 ★ さし木の利点
★ さし木の利点
① 植物体の一部を切り取ってさすだけなので簡単にふやせる。
② 茎・枝・葉など親木の一部を切ってさす無性繁殖なので親木と同じ形質のものをふやせます。
③ さし木をするには茎や枝の一部があればよいので一度に多くの苗をふやせます。
④ 実生苗などに比べれば、開花、結実がはやくなります。花が咲くようになった枝でさし木をすれば翌年から花を咲かせることもできます。
⑤ 八重咲き種などの園芸品種で種子のできないものでもふやすことができます。
 ※ さし穂の選び方
※ さし穂の選び方
さし木では切り取られた茎や枝など全く根のない部分から発根し、芽を伸ばしてひとつの個体に育ちます。
さし木を成功させるには再生能力、発根能力が大きいさし穂を選ぶことが重要です。
さし穂にはさし穂の内部にデンプンや糖分など栄養物質が多く蓄積されているほどよいとされています。
さし穂には日当たりのよいところでよく締まって生育した枝を選びましょう。
一本の枝でも新梢では先端部を、休眠枝では先端と基部を除く中間部を使います。
また、古い木より若い木の採穂した方がよく発根します。
※ さし床について
さし木を成功させるにはさし穂自身の発根能力とともに、さし床を発根しやすいようにととのえてやることが肝心です。
さし穂は下部の切り口からしか吸収できないのです。
用土には通気性、排水性、保水性がよく雑菌のない清潔な土を選びましょう。
保水性のよい赤玉土や通気性と排水性よい鹿沼土などが使われています。
他に通気性と排水性のよい川砂、保水性と通気性のよいバーミキュライト、パーライトなどを混ぜた混合土を使います。
園芸店にて色んな育苗箱が市販されているので自分の用途にあわせ排水のよいものを買いましょう。 平鉢や発泡スチロールの箱などでも構いません
 ※ さし木をする時期
※ さし木をする時期
さし木の適期は、さし穂の栄養状態や気温、湿度などの条件が良いときが最適の時期です。
☆ 落葉広葉樹
2~3月に前年枝をさす春ざし、6~9月初旬までに新梢をさす梅雨ざし、夏ざしが行われます。
☆ 常緑広葉樹
充実した前年枝をさす3月中旬~4月上旬の春ざし、新梢が固まった6~7月の梅雨ざし、9月の秋ざしが行われます。
☆ 常緑針葉樹
新梢が動き出す前の前年枝をさす 4~5月上旬の春ざし、7~9月に新梢をさす梅雨ざし、夏ざしがあります。
※ さし木をした後の管理
さし木ごは明るい日陰に置き十分に水やりをしましょう。水やりはさし穂がしおれないよう程度にやります。 さし床の中が過湿になると発根障害を起こす場合がありますので十分注意しましょう。
植物によって10日~1ヶ月くらいで発根します。発根したら徐々に日に当てるようにしましょう。
さし穂が発根したら移植をします。 但し真夏や厳寒期の場合は枯れたり、生育不良になったりしますので翌春の2月~3月頃に移植した方が良いでしょう。

 HOME
HOME
